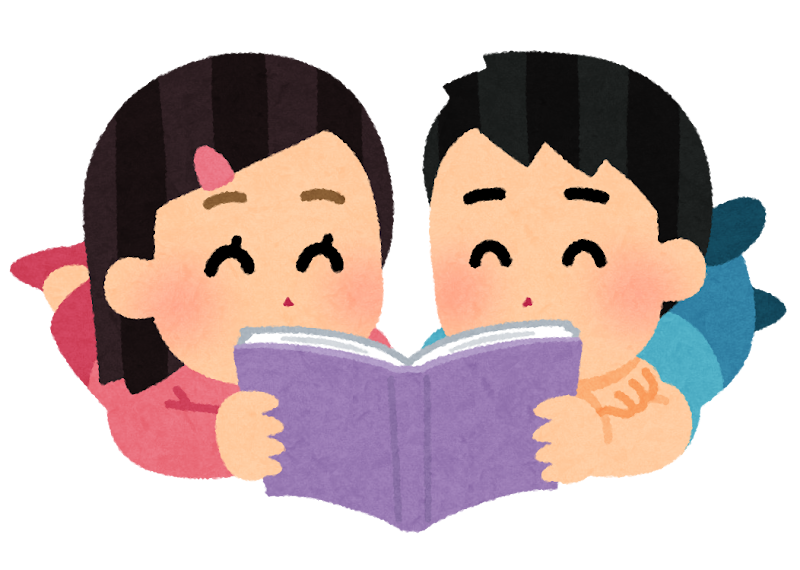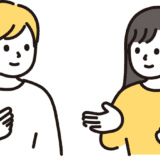「うちの子、文章を読むのが苦手みたい…」
「国語の成績が伸び悩んでいる…」
「そもそも『読解力』って、どうすれば鍛えられるの?」
こんにちは!元公立中学校・高校で理科教師をしていました、ひよどりです。現在は小中学生2児の母として、我が子の学習をサポートする日々を送っています。
保護者の皆さん、そして教育現場の先生方、こんなお悩みを抱えていませんか?
実は「読解力」は、単なる国語の成績だけの話ではありません。算数の文章問題、理科の実験レポート、社会の資料読解、さらには将来、情報を正しく理解し、自分の考えを伝えるための「生きる力」そのもの なんです。
今回は、私が教師時代の経験と、様々な書籍や研究で効果が示されている知見を基に、家庭や学校で今日から実践できる「読解力を鍛える6つの方法」を、具体的なアクションプランと共にご紹介します!
そもそも「読解力」とは?国語の成績だけではない本当の重要性
まず、少しだけ「読解力」について整理させてください。
読解力とは、ただ文字を追う力ではありません。OECD(経済協力開発機構)のPISA調査では、**「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」**と定義されています。
つまり、文章から情報を受け取るだけでなく、その情報を元に考え、活用する力が求められているのです。 これは、まさに今の学習指導要領で重視される「主体的・対話的で深い学び」の根幹とも言えます。
それでは、この大切な力をどう育めばよいのでしょうか?具体的な方法を見ていきましょう!
【実践法1】脳を活性化させる「音読」
一番手軽で、効果絶大なのが「音読」です。目で見るだけでなく、声に出し、耳で聞くという複数の感覚を使うことで、脳がグッと活性化します。
【家庭での実践例】
- 国語の教科書だけでなく、連絡帳の文章や給食の献立など、何でも一緒に声に出して読んでみる。
- 寝る前の5分間、好きな本の読み聞かせを親子で一行ずつ交代で読む。
【学校での実践例】
- 朝の会や帰りの会で、日直が新聞のコラムや短い詩を音読する時間を作る。
- 理科や社会の重要語句が出てくる説明文を、ペアで音読し合う。
【Point!】 完璧にスラスラ読めなくても大丈夫。「声に出して読む」こと自体が、文字と意味を結びつける素晴らしいトレーニングになります。
【実践法2】文章構造を体感する「書き写し(写経)」
少し地道ですが、書き写しは文章の構造を身体で覚えるための強力な方法です。主語と述語の関係、接続詞の使い方、句読点の打ち方など、名文を書き写すことで自然とインプットできます。
【家庭での実践例】
- お気に入りの本の好きなセリフや、心に残った詩をノートに書き写す。
- 新聞の「天声人語」や「編集手帳」など、短いコラムを週に1回書き写す習慣をつける。
【学校での実践例】
- 漢字練習の時間に、その漢字が使われている優れた短文を一緒に書き写させる。
- 詩や俳句、古典の冒頭部分などを、丁寧に書き写す活動を取り入れる。
【Point!】 量をこなすことより、一字一句を丁寧に書くことが大切です。「この読点にはどんな意味があるんだろう?」と考えながら書くと、さらに効果がアップします。
【実践法3】理解を深める「対話」
読んだ内容を自分の言葉で誰かに話す。これこそ、理解を本物に変えるためのカギです。話すことで頭の中が整理され、相手からの質問で新たな視点に気づかされます。
【家庭での実践例】
- 夕食の時に「今日読んだ本、どんな話だった?」と聞いてみる。
- 一緒に見たニュースについて「〇〇はどう思った?」と感想を尋ね、親の意見も伝えてみる。
【学校での実践例】
- 読んだ物語の登場人物の気持ちについて、グループで話し合う。
- 説明文を読んだ後、「つまり、どういうこと?」をペアで説明し合う活動(ペア・ラーニング)を行う。
【Point!】 親や先生が答えを教えるのではなく、**「どうしてそう思ったの?」**と問いを重ね、子どもの思考を深める聞き役に徹するのがコツです。
【実践法4】要点を見抜く力を養う「要約」
長い文章の中から「何が一番重要か?」を見つけ出し、短い言葉でまとめるのが「要約」です。情報があふれる現代社会で、必要な情報を選び取る力に直結します。
【家庭での実践例】
- 読んだ昔話のあらすじを**「3つの文で教えて!」**とお願いしてみる。
- テレビ番組を見た後、「今日のハイライトは何だった?」と聞いてみる。
【学校での実践例】
- 各段落に短い見出し(小見出し)をつけさせる活動。
- 単元の学習の最後に、学んだことを200字程度でまとめる学習レポートを作成する。
【Point!】 最初はうまくできなくて当然です。「誰が」「何をした」といった基本要素を押さえることから始めましょう。
【実践法5】能動的な読書に変わる「質問する」
「なぜ?」「どうして?」――。この問いを持つだけで、受け身の読書が、能動的な探求に変わります。文章の表面だけでなく、その裏側にある筆者の意図や背景まで考えるきっかけになります。
【家庭での実践例】
- 本を読みながら「もし君が主人公だったらどうする?」と問いかける。
- 図鑑を見ながら「なんでこの恐竜は首が長いのかな?」と一緒に疑問を言葉にしてみる。
【学校での実践例】
- 教科書を読みながら、疑問に思ったところに付箋を貼らせる。
- 単元の最初に、その単元で知りたいこと(問い)を子どもたち自身に立てさせる。
【Point!】 答えがすぐに見つからなくても構いません。「問いを持つ」こと自体が、思考のエンジンをかける大切な一歩です。
【実践法6】展開を読む力をつける「予測する」
タイトルや挿絵、最初の数行から「この後どうなるんだろう?」と予測しながら読む習慣は、読書への集中力と関心を高めます。
【家庭での実践例】
- 絵本の表紙を見せて「どんなお話だと思う?」と想像を膨らませる。
- 物語のクライマックスの前で一度本を閉じ、「結末はどうなると思う?」と話し合う。
【学校での実践例】
- 説明文の導入部分を読んだ後、「筆者はこの後、何を説明すると思う?」と問いかける。
- 物語の登場人物の行動から、「この人は次にどんな行動を取るだろう?」と予測させる。
【Point!】 予測が当たっても外れても、どちらも素晴らしい学びになります。「なぜそう思ったのか」を言語化させることが重要です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. そもそも本を読むのが嫌いな子はどうすればいいですか?
A1. 無理に活字の本を読ませる必要はありません。まずはマンガや図鑑、ゲームの攻略本など、お子さんが興味のあるものから始めましょう。「文字を読んで内容を理解する」という経験を積むことが第一歩です。そこから少しずつ、興味に合った物語や解説文に繋げていきましょう。
Q2. 何歳くらいから始めるのが効果的ですか?
A2. 思い立った時が始め時です! 今回ご紹介した方法は、幼児期の絵本の読み聞かせから、中学生の論説文読解まで、発達段階に応じてアレンジできます。例えば、幼児期は「音読」や「対話」を中心に、学年が上がるにつれて「要約」や「質問」を取り入れていくのがおすすめです。
まとめ:読解力は一生モノの財産。今日からできる一歩を始めよう!
ご紹介した6つの方法は、特別な教材がなくても、日常の会話や日々の学習の中で意識するだけで実践できるものばかりです。
- 音読:声に出して脳を活性化
- 書き写し:文章の型を身体で覚える
- 対話:自分の言葉で説明し、理解を深める
- 要約:要点を見抜く力をつける
- 質問する:受け身から能動的な学びへ
- 予測する:展開を読む力を養う
読解力は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、家庭と学校が連携し、日々の生活の中でコツコツと種を蒔き続けることで、子どもたちの内側にしなやかで力強い思考の幹が育っていきます。
ぜひ、この記事をブックマークして、一つでも試してみてください。そして、実践してみた感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです!