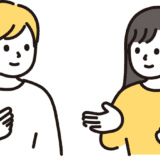「あの人、どうして空気が読めないんだろう…」
「言わなくてもわかるのに、どうして伝わらないんだろう…」
職場や学校で、発達障害を持つ人とのコミュニケーションに悩んだことはありませんか?
もしあなたが、「彼らがもっと努力すべきだ」と考えているなら、少し立ち止まって考えてみませんか。実は、問題解決の鍵は、マジョリティ(多数派)である私たち自身の関わり方にあるかもしれません。
この記事では、発達障害とのより良いコミュニケーションを実現するために、マジョリティが知っておくべき3つのポイントを解説します。
発達障害とのコミュニケーション、なぜマジョリティが学ぶべきなの?
私たちは無意識のうちに、「普通」という名の暗黙のルールを、コミュニケーションの場で相手に求めてしまいます。しかし、発達障害を持つ人にとって、この「普通」を理解し、身につけることは、とても大きな負担です。
彼らだけに一方的な努力を求めるのではなく、マジョリティである私たちが歩み寄ることで、誰もが生きやすい社会を目指すことができます。これは決して「特別な配慮」ではありません。お互いが尊重し合い、気持ちよく過ごすための、ほんの少しの工夫なのです。
知っておきたい!コミュニケーションの3つのヒント
では、具体的にどのようにコミュニケーションをとれば良いのでしょうか。今日から実践できる3つのヒントをご紹介します。
1. 曖昧な表現を避ける
「適当に」「早めに」といった曖昧な指示は、人によって解釈が異なります。特に発達障害を持つ人にとっては、具体性に欠ける指示は大きな混乱を招きます。
- NG例: 「この資料、早めにまとめておいて」
- OK例: 「この資料を、今日の午後3時までにメールで送ってください」
このように、期限や具体的な作業内容を明確に伝えることで、スムーズに仕事を進めることができます。
2. 指示は一つずつ、丁寧に伝える
一度に多くの指示を出すと、どこから手をつけて良いか分からなくなりがちです。一つの作業が終わってから次の指示を出すように心がけましょう。
- OK例: 「まず、Aの書類をコピーしてください。それが終わったら、Bのファイルに綴じてください」
3. 「なぜ?」と決めつけない姿勢を持つ
「なぜ空気を読めないの?」と相手を責めるのではなく、「ああ、そういう特性があるんだな」と理解しようとする姿勢が大切です。
感情的に反応するのではなく、「何か困っていることはありますか?」と冷静に問いかけることで、相手も安心して状況を説明できるようになります。
マジョリティが学ぶことで得られる2つのメリット
私たちがコミュニケーションを学ぶことは、相手のためだけではありません。私たち自身の人生をより豊かにするメリットがあります。
- コミュニケーションの幅が広がる: 多様なコミュニケーションスタイルを知ることで、あらゆる人と円滑な関係を築けるようになります。
- 新しい視点に気づく: 自分とは異なる価値観や考え方に触れることで、これまでの固定観念が壊れ、新しい発見や創造性が生まれます。
まとめ
発達障害の人とのコミュニケーションは、決して難しいことではありません。
マジョリティが、ほんの少しの歩み寄りと理解を示すだけで、お互いの世界は驚くほど広がります。
あなたのその「普通」を一度見つめ直してみませんか?