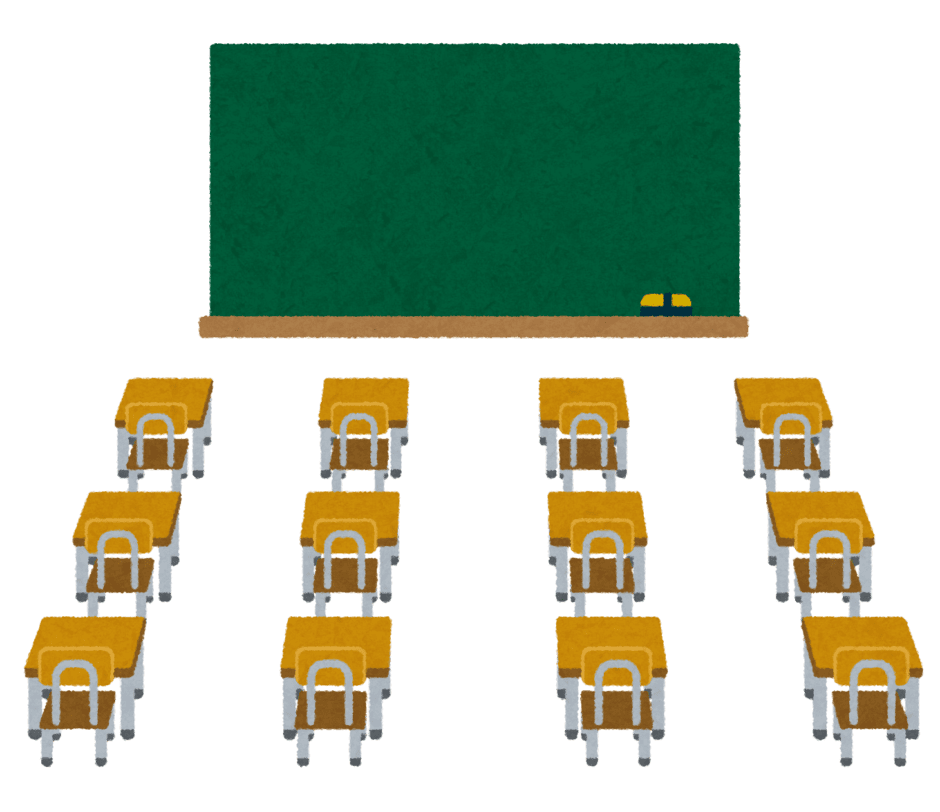「なぜ最近の学校はこんなに変わったの?」
お子さんがいるご家庭では、そんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。実は、私たち保護者世代が受けてきた学校教育と、今の子どもたちが受けている教育は、根本的に大きな違いがあります。
この違いを理解するためには、まず私たちがどのような教育を受けてきたのかを振り返ることが大切です。今回は、主に40代の筆者自身が経験してきた学校教育を中心に、その特徴と「負の影響」について掘り下げていきます。
- 保護者世代が受けた「旧来の教育」の特徴
- その教育がもたらした「負の影響」
- 変化した教育を理解するために、保護者ができること
私たち保護者世代が受けた「学校教育」の特徴
日本の学校教育は、おおよそ10年ごとの学習指導要領の改訂によって変化してきました。この改訂は、その時代の教育の課題を解決しようとする目的があります。
もちろん、過去の教育がすべて悪かったわけではありません。しかし、今振り返ると、社会の変化に十分に対応できていなかった側面があるのも事実です。以下に、当時の教育がもたらした「負の影響」についてまとめました。
1. 一律のカリキュラムと画一的な評価
- 個性の軽視:自分の興味や関心を探求する機会が少なく、個性が育ちにくい環境でした。
- 自己肯定感の低下:成績や学力で評価されることが多く、基準に満たないと感じた子どもは自己肯定感が低くなりやすい傾向がありました。
- 受け身の学び:創造性や主体性が重視されず、「先生の話を聞いて覚える」ことが中心でした。
2. 点数至上主義と偏差値競争
- 詰め込み型教育:知識を暗記することが重視され、「なぜそうなるのか」を考える力が育ちにくかったと言えます。
- 学ぶ楽しさの喪失:点数や合格実績が目標となり、本来の「学ぶことの楽しさ」を感じにくくなりました。
3. 教師中心の一方通行な授業
- 主体性の欠如:生徒が自ら問いを立てたり、議論したりする機会がほとんどありませんでした。
- 協調性の不足:グループワークやチームでの課題解決の経験が乏しく、社会で求められるコミュニケーション能力や協調性を養うことが難しかったと言えます。
4. 厳格な校則と管理
- 多様性の抑圧:自己表現や個性を受け入れる文化が育ちにくく、人と違うことへの同調圧力が生まれやすい環境でした。
- 思考力の低下:権威やルールに対して疑問を持つ機会が少なく、批判的思考力を養うのが難しい側面もありました。
5. 時代に追いつかない教育内容
- 実践的スキルの不足:デジタルリテラシーや英語でのコミュニケーション能力など、実社会で役立つスキルを学ぶ機会が少なかったです。
6. 固定観念を助長する教育
- ジェンダー平等の遅れ:「男は外で働き、女は家庭を守る」といった価値観が、知らず知らずのうちに子どもたちに影響を与えていました。性的少数者や多様な家族形態への理解も不十分でした。
まとめ:旧来の教育がもたらしたもの
こうした旧来の教育は、日本の高度経済成長期に、均質な労働力を大量に育成するうえで大きな役割を果たしました。しかし、その一方で、「みんなと同じ」であることが良しとされ、人との違いが目立ち、失敗を恐れる文化を生み出してしまったと言えるのではないでしょうか。
保護者世代が「今」できること
過去の教育を振り返ってみて、どのように感じましたか?
もちろん、個人の経験や学校、先生によって教育のあり方は様々です。しかし、旧来の教育がもたらした「負の影響」を理解することは、これからの子どもたちの学びを考える上で非常に重要です。
大切なのは、子どもたちに「画一的な環境」を強いるのではなく、「多様な経験や選択肢のある環境」を提供することです。そして、私たち保護者自身が、時代の変化に敏感になり、学び続ける姿勢を持つこと。
社会全体が大きく変化する現代において、子どもたちがより良い未来を生き抜くために、大人が率先して考え、行動することが求められています。
次回は、新しい教育のキーワードである「学力観」について、さらに詳しく掘り下げていきたいと思います。
あなた自身が受けた教育を振り返ってみて、今の子どもたちの学びについて、どのようなことを感じますか?